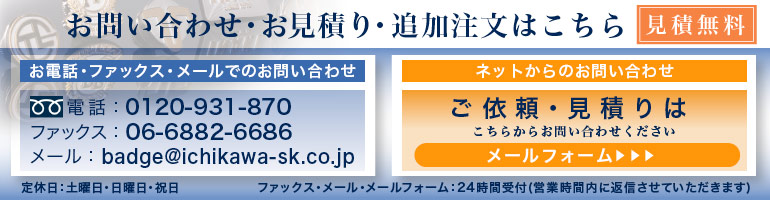「徽章(きしょう)」という言葉を耳にしたことはありますか?「聞いたことがない」「あまりよく知らない」という方も多いかと思います。しかし日本で「徽章」という言葉が生まれたのは明治8年の頃であり、非常に古い歴史をもったものなのです。
本記事では社章バッジコラムとして、社章とは違う「徽章」とはどのようなものなのかについて、その歴史を紐解きながらご紹介していきます。
「徽章」とは
「徽章」とは、本来は騎馬武者が担ぐ「旗印」のことを指しているのですが、現在では身分・資格といったことを示すしるしのことを意味する言葉となりました。その印は帽子・衣服など、身に付けるバッジを意味しています。
徽章の役割としては、自分が有する職務・資格・技能と言ったものを示すためにあるものです。
周りの人が身に付けた徽章を見て、その立場を理解できるというメリットもあります。
徽章を身に付けることによってその人の意識が高まって、態度・行動といった面で世間に恥ずかしくないように振る舞うという効果もあります。
徽章の歴史について

諸説はありますが、「徽章」の歴史はおおよそ西暦600年から始まったと言われています。
日本では1875年に制定された文書で「徽章」の文字を確認することができます。
日本では古くからさまざまな武具が用いられてきたのですが、明治期の文明開化を始まりとして、西洋文化が急速に広がっていくこととなりました。
これまで武具で使われてきた紋章・家紋といったものが、職人の手が加えられたことによってボタン・装身具といったものへと変わっていきます。
徽章はこれまで「金工師」や「錺師(かざりし)」と呼ばれる職人の手で育まれてきました。
東京では徽章を専門に扱う「徽章屋」が登場し、横浜や名古屋、大阪の方面へと広がっていきました。
当時比較的安定した職業であった徽章屋は、錺師の多かった浅草・下谷のエリアを中心に活気付いていたのです。
その後、昭和の時代に入ると太平洋戦争が開戦したことによって、軍関係の受注が続き、民間業者が勲章を思うように製造することができなくなってしまうのです。
そのような徽章業界で大きな転機があったとされているのは、1964年に開催された東京オリンピックです。
オリンピックの象徴であった「五輪」をあしらった製品を多く製造するために、全国記章事業推進会が発足し成功へと導いたのです。
徽章作りに関係する人々は、東京オリンピックが開催された後も日本で開催されるさまざまなイベントを陰で支えているのです。
「社章」との違いは何?

「社章」とは、身分でなく、その会社の一員ということを示すものです。
「徽章」と「社章」の違いとしては、徽章は組織においての身分を示すために用いられることがありますが、社章は身分を示すものでなくて、単純にその組織のロゴマークをしるしたものであるという違いがあります。
会社名・企業ロゴといったものがデザインされていて、ひと目見ただけもその会社の社員であるということが分かるでしょう。
社章の代わりとしてカードのような身分証明書を取り入れている企業もあり、その活用のされ方はさまざまなものがあります。
また、部署・階級により異なるという場合には、徽章のような意味合いを持つケースもあります。
おわりに
本記事では社章バッジコラムとして、社章とは違う「徽章」とはどのようなものなのかについてご紹介しました。
歴史の古い「徽章」。元々は騎馬武者の担ぐ「旗印」を意味していたとされている徽章ですが、時代の流れや装身具の変化により、一層発展を遂げてきました。
社章とは異なるものではありますが、「自身を指し示す」という意味ではどちらも共通しているものですね。
社章バッジ関連